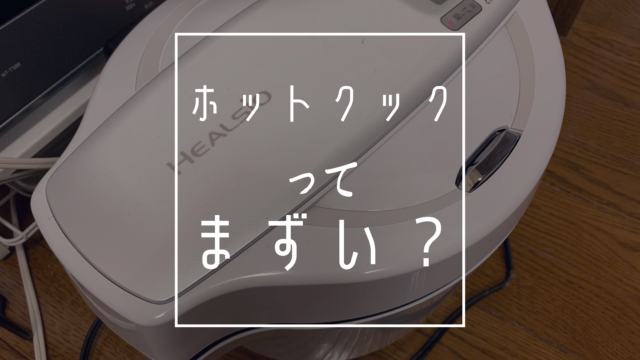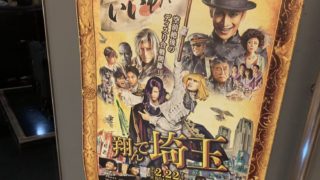定期的に本レビューを行っていますが、最近はこの「ファクトフルネス」という本を読んでいました。
ファクトフルネスの共訳者です。ぜひお手にとってみてください!
— Shu Uesugi (@chibicode) 2019年1月19日
きっかけはこれ。
面白かった記事のツイートしたら、共訳者(上杉周作さん)の方からコメント頂き、これは読んでみよう!と。
そして個人的にヒットした本だったので、レビューを書いてみます。
凄くざっくり言うと「事実や一次情報でしっかり判断して、情報に踊らされないようにしよう」というような内容なんですけど、これが物凄い現代に必要な考え方だと思うんです。
確かに言葉だけで見たら「当たり前だろ」と思うかもしれません。
でも意外と情報が氾濫している時代では簡略化された二次、三次情報が飛び交っており、知らぬ間にそれをファクトとして把握しているものも少なくないはずです。
もちろん二次情報、三次情報でも収集する上では全く問題ないと思うのですが、情報が正しくまとめられているのか、主観や偏見が入っていないかは意識しておきたいですよね。
目の前にあるデータを、正しく把握出来ているかを改めて考えさせられる一冊でした。
というような感じで、今日はこのファクトフルネスについてまとめていこうと思います。
データを見ても「世界はどんどん悪くなっている」と言い切れるのか
 AdinaVoicu / Pixabay
AdinaVoicu / Pixabayまずこの本で驚いたのは、実は世界はどんどん良くなっているという「ファクト」を見せられたことです。
細かなデータに関しては是非本を手にとって確認して欲しいのですが、例えば「ここ20年の間に極度の貧困層の割合が半減している」というデータであったり、僕たちが学校の授業などで学んだ「先進国・発展途上国」という線引きは既に無くなっていることを示すデータの紹介もあります。
私たちが知っている先進国・発展途上国の線引きについては、本の中では1965年の国ごとの女性一人当たりの子供の数と乳幼児生存率を示したものと酷似しています。
同様のデータの2017年版を確認すると、発展途上国と言われる場所に該当する国はほとんどありませんでした。
あとこれはちょっと余談なんですけど、色んなデータを確認していると、ふと過去に色々と問題視されていた「オゾン層の破壊」について思い出したんですよね。
興味本位で調べてみたら、今ってオゾン層は回復してきているようで、少しずつのようですが南極のオゾンホールは閉じつつあるみたいなんです。
で、こういうポジティブな経過報告って、なんで伝わってこないんだろうと疑問に思うんですよ。
そして、これこそがファクトフルネスで最も言いたいことの1つだったのではないかとも思うわけで……。
なぜ「世の中はどんどん悪くなっている」と勘違いしてしまうのか
 qimono / Pixabay
qimono / Pixabay見出しに書いた通りなのですが、こういう「思い込み」「勘違い」はどうして起きるのか?ということにも踏み込んで書かれていました。
本書ではネガティブ本能・分断本能などといった表現でまとめられていますが、勘違いを引き起こす原因の1つが「マスメディア」であると分かります。
例えば人間は物事が少しずつ良くなっていく様子よりも、何か大きな事件を取り上げた方が注目してしまいますし、それが視聴率やページのアクセスに繋がっていくので、悪い噂を積極的に取り上げる傾向があります。
本書でも1990年以降、実はアメリカの犯罪発生率は減り続けているものの、ショッキングな犯罪は毎年のように起こり、そのタイミングでメディアが大々的に報道する点をピックアップしていました。
その結果私たちは「犯罪は減っていない」「増えている」という思いこみをしてしまいがちで、こういった要素が積み重なって世界はどんどん悪くなっていると錯覚する人が増えているのでは? と論じていました。
低い評価に引っ張られて、買うのやめる気持ちはすごくよくわかる。私も何か買う時に、つい良いレビューよりも悪いレビューに引っ張られる。ツイッターで、応援以上にネガティブツイートが心に深く残ってしまうのに似てる。ネガティブにはプラスを無かったことにするくらいの強力なパワーがある。
— はあちゅう (@ha_chu) 2019年2月16日
これは比較的身近な、良いメッセージよりも悪いメッセージの方が刺さる典型例。
アマゾンのレビューでも悪い評価の方が何故か見入ってしまって、良い評価は意外と記憶に残らない、というケースに心当たりがある方も多いのではないでしょうか。
このようにメディアは、自分たちの情報を見てほしいために、時として意図的にネガティブなニュースを切り取って発信する傾向があります。
悪い部分だけにとらわれず、良い部分も把握した上で、両者を天秤にかけるフラットな考え方が必要なのだろうと、読みながら感じていました。
池江璃花子選手と桜田五輪相の一件はメディアのあり方を考えさせられる事案
 geralt / Pixabay
geralt / Pixabayここからは本書の内容から逸れますが、「思い込み」について書くにあたって取り上げておきたい項目を紹介します。
少し前に池江璃花子選手が病気を公表された時に桜田五輪相が「がっかりした」と非難したとされるニュースが出回ったのは記憶に新しいと思います。
それはマスメディアでも各所に拡散され、テレビでもコメンテーターが痛烈に批判していました。
確かに桜田五輪相を批判した形の記事を読むと「とんでもないな…」と思ってしまいそうになりますが、全文の記事を読むと、また印象が変わってきます。
マジでマスコミくそ。 https://t.co/NM51cbLVVU
— 堀江貴文(Takafumi Horie) (@takapon_jp) 2019年2月14日
これは問題発言があったとされるインタビューの全文がまとめられている記事です。
こちらを見ると「そんなに波風立てるべき内容か?」と思いますし、人によっては「どこが悪いの?」と思うのではないでしょうか。
これをファクトフルネスの考えと当てはめてみると、メディアが人間の本能を駆り立たせるような形で文章を作ったんだろうなぁとも考えさせられますよね。
本当に情報を正しく噛み砕けているのか?
このように、全文を見ると全く何でもないようなことにもかかわらず、メディアの過剰な揚げ足取りにより文章を大げさにネガティブにすることによって、社会全体がネガティブに見えやすいんだろうなと感じています。
ファクトフルネスで学んだことは他にもまだありますが、データや事実に注視する重要性を改めて考えさせてくれる良書でした。
これは自分の主観も入っていますが、こういった「悪い情報への流されやすさ」というのは、日本人の致命的な欠点だと思います。本質から逸れた形で物事を見てしまうことで、本当に正しい情報を取得する機会を逸してしまうかもしれません。
今後はこういったファクトを追って物事を見ることができる人と、そうでない人との間に差が出てくるのではないでしょうか。